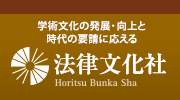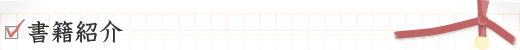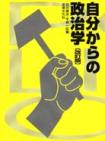
| ���Ж� | ��������̐����w�k�����Łl |
|---|---|
| ���� |
�ΐ쏷���E �����b�� |
| ���^ | �l�Z�� |
| �� | 310�� |
| ���s�N�� | 1999�N9�� |
| �艿 | 2,970�~�i�ō��j |
| ISBN | ISBN4-589-02166-8 |
| �{�̐��� |
�����i����̏�j�Ɛ����Ƃ̂��������A�����E���j�E����E�v�z�̂S�̃L�[���[�h�����Ƃɖ��炩�ɂ���B�ٕ����E�W�F���_�[�A���{�ƃA�W�A�̐��A�j�̎���ƕ��a�v�z�Ȃǐg�߂Ȗ���f�ނɕ��ՂɓW�J�B���ňȍ~�̕ω����ӂ܂��ĉ����B ���̏��Ђ͕i�ɂ�����ł��܂��� |
| �ڎ� |
�v�����[�O�@�u��������̐����w�v�ɂނ��� �@�@��@�̂̎�҂ƍ��̎�� �@�@��@�u��������v�o������ �@�@�@���̎�҂̂���ꏊ �@�@�@���x�o�ϐ�����̎Љ� �@�@�@�l�̈ꐶ�Ɛ��� �@�@�@�u��@�v�̎��ォ��̖₢���� �@�@�O�@�u���I����]�����v�Ǝ����� �@�@�@�n���I�K�͂̊�@ �@�@�@��H�ɗ������� �@�@�@�u��������̐����w�v���n�߂悤 �@�@���R�����@��w�|�s�v�c�̍��̃��W���[�����h�i�]�����m�j �T�@�����ւ̗� �@�P�@�ٕ����Ɛ��� �@�@�@�@�����ƕ����́u�Փˁv����������Ȃ��̂��H �@�@��@�ٕ������̏o���_ �@�@�@�ٕ����́u�Փˁv �@�@�@�ٕ��������l���鎅�� �@�@�@�����Љ���߂����čl���� �@�@�j�@�t�����X�ٕ̈������ �@�@�@����ꂽ�������� �@�@�@������`�̌�� �@�@�@�V�����ٕ������̎n�܂� �@�@�@�������Ɨ��O�Ɋ�Â����� �@�@�@�u���قւ̌����v �@�@�@�u�����ւ̌����v �@�@�@�u�V�����l���`�v �@�@�@�ǂ̂悤�ȃt�����X�Љ������̂� �@�@�O�@���{�ɂ�����ٕ������̌��� �@�@�@�O�ٕ̈������ �@�@�@��Z���Ƃ��ẴA�C�k���� �@�@�@��Z�O���l�Ƃ��Ă̍ݓ��؍��E���N�l �@�@�@�O���l�J���� �@�@�@�ǂ̂悤�ȓ��{�Љ������̂� �@�@�l�@�����Љ������ �@�@���R�����F�u�����v�Ƃ́H�i�o���O�j �@�Q�@�W�F���_�[�E�|���e�B�N�X �@�@�@�@�����ƒj���́u�v�Ƃ��ďo��邩�H �@�@��@���Ɛ������߂����� �@�@��@��ƂƏ��� �@�@�@�j���ٗp�@��ϓ��@ �@�@�@�Ȃ��A�����͍̗p����Ȃ����H �@�@�O�@�ی�ƕ��� �@�@�@�����ی�K�� �@�@�@��Ǝ�w�u�ی�v���� �@�@�l�@�J���Ɛ� �@�@�@�Z�N�V���A���E�n���X�����g�Ƃ́H �@�@�@�Z�N�n���ٔ��̖₢��������� �@�@�܁@�Ƒ��Ɛ� �@�@�@�Y�ސ����ꐫ������ �@�@�@�v�w�ʐ� �@�@�Z�@�j�������Љ������ �@�@���R�����F�Љ�ւ͂������������ցi�c�����q�j �U�@���j�ւ̗� �@�R�@���{�̐�� �@�@�@�u��㍑�Ɠ��{�v�͂ǂ��ɂ��ǂ�����̂��H �@�@��@������̌����� �@�@��@�p�Ђ���̖����` �@�@�@�����v �@�@�@��̐���̓]�� �@�@�@�u�܌ܔN�̐��v �@�@�O�@�u�ɉh�v�̎���Ɨ��v���� �@�@�@���x���� �@�@�@�����}��}�D�ʑ̐� �@�@�@�u�ɉh�v�̉e �@�@�@�v�V�����́E�x�g�i���E���� �@�@�l�@�u�ɉh�v�̂�炬�Ɛ����̍��� �@�@�@���x�����̏I�� �@�@�@�V�ێ��`�̓W�J�ƍ��� �@�@�@�u���a�v�̏I�� �@�@�@�����}��}�D�ʑ̐��̕��� �@�@�܁@���I���̓��{���� �@�@���R�����F�u�����a�̐����w�v�i�����M�v�j �@�S�@�A�W�A�̐�� �@�@�@�������Ƃ͂ǂ��ϗe����̂��H �@�@��@�u�P���v�V������ �@�@�@�V���Ɨ����̒a�� �@�@�@���̔g�y �@�@�@�o���h�����_ �@�@��@�u�����r�v�ɂ�鍑�Ƃ̕ϗe �@�@�@�u�����r�v�o��̔w�i �@�@�@�u�����r�v�ɂ�鍑�Ɖ^�c �@�@�@��Ղ̌o�ϐ��� �@�@�@�Љ��`���Ƃ́u�_�̘r�v �@�@�O�@�F������u�����r�v �@�@�@���o����ًc�\������ �@�@�@���݂ɂ���ꂽ�ًc�\������ �@�@�@�A�W�A�o�ϊ�@�Ɩ��剻 �@�@�l�@�A�W�A�̋������ƂƓ��{ �@�@���R�����F�w�҂��琭���Ƃցi�������j �V�@����ւ̗� �@�T�@���������`�̂�炬�Ɩ����`�̂䂭�� �@�@�@�V�����������͐�����ς��邩�H �@�@��@���㐭���̃p���h�b�N�X �@�@�j�@�t�H�[�f�B�Y���Ǝ��R�����`�̐� �@�@�@���R�����`�̐��̂��ƂŐ����� �@�@�@�u���_���E�^�C���X�v �@�@�@�`���b�v�����t�H�[�h �@�@�@��ʏ�����̖��ƌ��� �@�@�@�P�C���Y��`�������� �@�@�@�J���g�� �@�@�@���} �@�@�@�o�b�N�X�E�A�����J�[�i �@�@�O�@�t�H�[�f�B�Y���̊�@ �@�@�@�t�H�[�f�B�Y���ƃP�C���Y��`�������Ƃ̖��� �@�@�@���R�����`�̐��̂�炬 �@�@�l�@�|�X�g�E�t�H�[�f�B�Y���̖͍� �@�@�@�R�[�|���e�B�Y���헪 �@�@�@�V�ێ��`�헪 �@�@�@�V�����Љ�^���ƐV�������� �@�@�܁@�����`�ƌl�����̍Đ��Ɍ����� �@�@���R�����F����낤�@�ω��̎���Ɂi����j���j �@�U�@���o���閯����� �@�@�@���������͖��\���H �@�@��@���I���Ɓu�p���h���̔��v �@�@��@�������Ƃ͉��� �@�@�@�������̋N���Ɣw�i �@�@�@�����̒�`�Ɩ����Η��̍\�� �@�@�O�@�����[�S�����ɂ݂閯���Η��̋�̓I�l�� �@�@�@�����[�S�����̌o�܂Ɣw�i �@�@�@�A�M�̕���Ɠ���̔��� �@�@�@�����E�o�ϑΗ����疯���Η��� �@�@�@�����Η��̘A�������I�\�� �@�@�l�@���ێЉ�͏������̋����������ł��邩 �@�@�@���Ə��F�Ɩ��������̌��� �@�@�@���A���a�ێ������̓����Ɩ��_ �@�@�@�������̋����Ɍ����� �@�@���R�����F���[�S�X�����B�A�̔ߌ��i�x�C�����B�`�E�`���X���t�j �@�V�@�]�����鐢�E���� �@�@�@�n�}�͕ς��H �@�@��@�n�}�̂Ȃ��̐��� �@�@�@�n�}�̕��� �@�@�@���k�A�W�A�̎l�̍� �@�@�@���ꂽ���[���b�p �@�@�@���Ɠ��k�A�W�A �@�@�j�@���ƎЉ��` �@�@�@���̐��E�� �@�@�@�Љ��`�̐��Ɓu�����v �@�@�O�@�|�X�g���ƍ��Ƃ̉��� �@�@�@�Љ��`�̐��̕��� �@�@�@�u�V���E�����v�̉A�� �@�@�l�@�����̂Ȃ��̒n�}�|���k�A�W�A�n�}�̓W�] �@�@���R�����FHuman�@Rights�@in�@East�@Asia�i�C�A���E�j�A���[�j �W�@�v�z�ւ̗� �@�W�@�u��R�v�Ɓu�����v�̊� �@�@�@�v�z�͉����Ȃ����邩�H �@�@��@�v�z���w�ԂƂ������� �@�@��@��l�̃m�[�x���܍�� �@�@�@��]���O�Y �@�@�@�}���^���E�f���E�K�[�� �@�@�O�@����vs�l�� �@�@�@���߂Ɍ��肫 �@�@�@��R�̑��� �@�@�l�@�����̊�w �@�@�@���߂Ɍ��t���肫 �@�@�@�u���Y�点�c�c�v�����͐� �@�@�܁@�v�z�Ƃ��Ă̐��� �@�@�@�����͉�������H �@�@�@������n�� �@�@���R�����F�n��ōl���镁�ʂ̐����i�����@���j �@�X�@�j�̎���ƕ��a�̎v�z �@�@�@�u�j���v�͂��������z�����̂��H �@�@��@�u�j�̎���v�̎n�܂� �@�@��@���������i���q�����j �@�@�@���q�͂Ȃ������ڕW�Ƃ��ꂽ�̂� �@�@�@�Ȃ������͏��q�ɓ�������Ȃ������̂� �@�@�O�@���E�̔픚�� �@�@�@�Đ��{�Ɠ��{���{�̑Ή� �@�@�@�����m�E�r�L�j�|���{�l�����O�x�ڂ̊j�i�����j�̎S�� �@�@�@�L����j�푈�����̂��߂̐l�̎����Ɗj��Q �@�@�@���\�A �@�@�l�@�u�j�̎���v�̌��i�K �@�@�@�j�̊�@�͉��̂����̂� �@�@�@�j�̎���̑�� �@�@�܁@�j�E���ƁE�l�� �@�@�@�j�|�l�ԂƋ����ł���̂� �@�@�@���Ɓ|���{�͔�j���ƂȂ̂� �@�@�@�l�ԁ|�q���V�}�E�i�K�T�L�̎v�z���ƌp�� �@�@�@���R�����F�픚�҂��l�����ɋ����Ă��ꂽ���́i���������j �X�@�����ւ̗� �@10�@�����������E���������� �@�@�@�u��������v�����Ă������ �@�@��@�Ƃǂ��ʐ� �@�@�@���R�̌����i�� �@�@�@�G�r�A�o�i�i�Ɠ��{�l �@�@�@���̂Ȃ��̃������b�g�H �@�@��@���Ԍn�̂Ȃ��́u�����v �@�@�@�G�R���W�[���̌��� �@�@�@�G�R���W�[���Ɠ�k��� �@�@�O�@�u�����v�͂ǂ��ɂ���̂� �@�@�@�u���E�V�X�e���_�v���`�����E �@�@�@���{�ɂ�����u���S�v�Ɓu�����v �@�@�l�@�n��̂Ȃ��́u�����v �@�@�@�Ȃ����܁u�n��v�Ȃ̂� �@�@�@�n�搭���̂��� �@�@�@�u�n��v�ւ̂������A�u�����v�ւ̂������ �G�s���[�O�@�ӂ����сu��������̐����w�v�� �@������ �@�����łɂ������� �@���@�� |