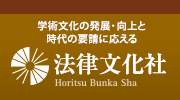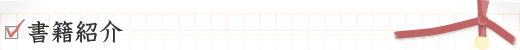| 書籍名 | はじめての民法 |
|---|---|
| 著者 |
中川淳・ 貝田守編 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 270頁 |
| 発行年月 | 2005年10月 |
| 定価 | 2,750円(税込) |
| ISBN | ISBN4-589-02878-6 |
| 本の説明 |
条文や図解を数多く盛り込み、民法全体をわかりやすく解説。判例を含め、現時点における理論的到達点を踏まえて基本的内容を概説する。民法の現代語化に対応。新たに「不法行為」の章を設けてより詳しく解説。 この書籍は品切につき入手できません |
| 目次 |
はしがき 序章 第一節 民法とは何か 一 私法の一般法 二 民法と民法の特別法 三 民法の基本的な考え方 第二節 民法典 一 民法典の沿革 二 民法典の構成 第三節 民法の解釈 一 民法の解釈の意義 二 解釈の方法 第四節 民法上の権利 一 法律関係と権利 二 民法上の権利の種類 三 民法上の権利の行使 第一章 総則 第一節 権利の主体 第二節 自然人 一 権利能力 二 行為能力 三 制限能力者 四 住所 五 不在者 六 失踪宣告 七 同時死亡の推定 第三節 物 一 権利の客体と物 二 物の意義 三 物の分類 第四節 法律行為 一 法律行為自由の原則 二 法律行為の意義 三 法律行為の分類 四 法律行為の解釈 五 法律行為の内容 六 無効と取消 七 条件と期限 第五節 意思表示 一 意思表示の意義 二 意思の欠缺 三 瑕疵ある意思表示 第六節 代理 一 代理制度 二 代理の意義と性質 三 代理権 四 代理行為 五 無権代理 第七節 時効 一 時効の意義と根拠 二 時効の効力 三 時効の中断・停止 四 取得時効 五 消滅時効 六 期間 第二章 物権法 第一節 物権法総論―物権とはどのようなものか― 一 人と物との関係 二 物権の作用と効力 三 物権変動について 四 即時取得 第二節 占有権 一 占有と占有権 二 占有権の成立要件 三 占有の種類 四 占有権の取得 五 占有権の消滅 六 占有権の効力 七 準占有 第三節 所有権 一 「所有権」とは 二 所有権の内容と性質 三 土地所有権と相隣関係 四 所有権の取得 五 共有 第四節 用益物権 一 用益物権とは 二 地上権 三 地役権 第五節 担保物権 一 総説―担保とは― 二 法定担保物権 三 質権 四 抵当権 五 非典型担保権 第三章 債権総論 第一節 債権とは 一 債権の特質 二 債権の多様性と発生原因 三 債権の目的による区別 第二節 債権の効力 一 契約違反・債務不履行 二 損害賠償 三 債権の保全 第三節 多数当事者関係 一 多数当事者関係 二 不可分債権・債務 三 連帯債務 四 保証債務 第四節 債権の移動 一 債権譲渡 二 債務引受 三 契約引受 第五節 債権の消滅 一 債権の消滅原因 二 弁済 三 相殺 第四章 債権各論 第一節 契約総論 一 契約 二 契約の成立 三 契約の効力 四 契約の解除 第二節 売買 一 売買の意義 二 特殊の売買 三 売買の成立 四 売買の効力 第三節 消費貸借 一 消費貸借の意義 二 消費貸借の効力 三 消費貸借の予約 四 準消費貸借 五 諾成的消費貸借 六 利息の制限 第四節 賃貸借 一 賃貸借の意義 二 存続期間 三 賃貸借の効力 四 賃借権 五 敷金・権利金 六 賃貸借の終了 第五章 不法行為・不当利得・事務管理 第一節 不法行為 一 一般の不法行為 二 不法行為責任とその救済 三 過失責任と無過失責任 第二節 不当利得 一 不当利得の意義 二 不当利得の性質 三 利得返還義務 四 不当利得の特則 第三節 事務管理 一 事務管理の意義 二 事務管理の性質 第六章 親族 第一節 家族と家族法 一 家族法の歴史 二 家族と親族 三 戸籍―家族関係の公示― 四 氏と名 第二節 夫婦 一 婚約と結納 二 婚姻の成立 三 婚姻の効果 四 婚姻の解消―離婚を中心として― 第三節 親子 一 実子 二 養子―特別養子制度― 三 親権 第四節 扶養 一 扶養の意義―私的扶養と公的扶養― 二 扶養の本質―生活保持の扶養と生活扶助の不要 三 扶養の内容―老親扶養― 第七章 相続 第一節 相続の根拠と相続制度 第二節 相続の開始と相続人 一 相続の開始 二 相続人 三 代襲相続 四 相続人の資格 第三節 相続の効力 一 権利義務の承継 二 相続分 三 遺産の分割 四 相続の回復 第四節 相続の承認と放棄 一 承認と放棄制度について 二 放棄 三 限定承認 四 単純承認 五 財産分離 第五節 遺言と遺留分 一 遺言の意義 二 遺言の方式 三 遺言の効力 四 遺言の執行 五 遺留分 事項索引 |