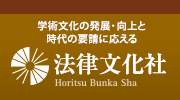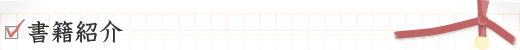| 書籍名 | 日本人のしつけ |
|---|---|
| 副題 | 家庭教育と学校教育の変遷と交錯 |
| 著者 |
有地亨著 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 232頁 |
| 発行年月 | 2000年6月 |
| 定価 | 1,980円(税込) |
| ISBN | ISBN4-589-02447-0 |
| 本の説明 |
相つぐ子どもの「問題行動」が大きな社会問題になっている。原因は何か。家庭の教育力の低下に注目し、その柱であるしつけを考察。戦前戦後の実態と変容を具体的に検討し、見直しといま必要なことを提起する。 この書籍は品切につき入手できません |
| 目次 |
はしがき 1 家庭教育力の低下 一九九八年の青少年非行調査などの結果 戦後の修身科目の廃止の経緯 道徳を学校教育の柱にすべきではないとする投稿に対する賛否両論 2 中央教育審議会の対応 一九九八年六月三〇日の答申 一九九八年九月二一日の答申 3 団塊の世代と次ぐ世代の子 団塊の世代と次ぐ世代の特徴 これらの世代の親たちの戦後の反省 団塊ジュニア世代とそれに次ぐ世代の子育て 引きこもる団塊ジュニア世代 団塊の世代の家族の郊外化 4 家庭教育におけるしつけ 『民俗学辞典』のしつけの意義 組織的しつけ慣行の消滅の時期 個々の家庭内のしつけ 5 家庭教育と学校教育との関連 家庭教育の衰退 さまざまの家庭教育論 一九二三年の家庭教育の欠落はなにで補われるか―新聞読者の投稿 学生の思想善導に利用された家庭教育 文部省による家庭教育の普及と振興政策 一九四一年、教育審議会による「家庭教育二関スル要綱案」の審議 家庭と学校の連携は未解決の今日的課題 6 確定しなかった修身科の教え方 当初の修身教授の方法 教科書の開申制度の採用 一八八二年の文部省達による教科書認可制の採用 一八八六年の教科書の検定制度の採用 森文相による修身教授につき教科書不採用の通牒 教育勅語の渙発 大木文相による修身教科用図書不採用の通牒の撤回 一八九一年の修身教科用図書の検定標準 修身教科書の国定化への動き 7 修身教科書の徳目と「道徳」の指導目標との関係 第一期から第五期国定教科書の使用状況 国定修身教科書の中の徳目の推移 修身教科書の編集方針 修身教育の方法 先学による修身教科書の徳目に関する研究 第一期から第四期国定小学校修身教科書の全題目 しつけの対象となる最低限の社会ルール 一九五八年の「道徳」時間の特設と指導目標 修身教科書の徳目と指導目標の符合 8 わが国における伝統的なしつけの慣行 一 明治より前の時代 財津種莢/小宮山楓軒/貝原益軒/橘守部/室鳩巣/手島堵庵/柴 田鳩翁/幼児は年に随ってすべからく教ゆべし 二 明治・大正・昭和戦前の時代 この時代の家庭内のしつけ 〔1〕父親 尾崎三良/内藤耻叟/棚橋一郎/大鳥圭介/本多庸一/加藤弘之/ 谷干城/尾崎行雄/三好退蔵/西村茂樹/副島種臣/清岡公張/渋 沢栄一の父親/福沢諭吉/犬養孝の父親/土田国保の父親/吉川英 治/笠智衆の父親/小森和子の父親/桑原武夫の父親/大町文衛の 父親・大町桂月/庄司吉之助の父親/太田文平の父親/朝吹登水子 の父親/宮城まり子の父親/黒岩重吾と父親/藤原ていの父親 〔2〕母親 田中正造の母親/神鞭知常の妻/貝塚茂樹の母親/岩田専太郎の母 親/志村喬の母親/五所平之助の母親/田村魚菜の母親/岡本太郎 の母親かの子/村山りうの母親/植村直己の母親/林真理子の母親 〔3〕祖父母 志賀かう子の祖母ミヱ/若山喜志子の祖母/長與専斎の祖父/片岡 健吉の祖父/丸岡秀子の母方の祖父母/田中生夫の母方の祖父 9 しつけのキーワード 時空間を超えた原体験としてのしつけ しつけの役割は分担される しつけは年齢に応じて幼いときから実施すべきである しつけは厳しくすべきである 子どもの違反行為には制裁を伴うことがある 親自らが子どもに対し模範を示す必要がある 礼儀作法のしつけは厳しくなすべきである うそをつかないというのが重要な徳目である 子どもには家事を分担させる しつける者は明確な信条をもってしつけをする 10 現今の家庭内のしつけ 一 いまの子の状況 「学級崩壊」の発生 受験態勢、大学制度の改革の必要性 少年法改正の動き 子どもの人格の見直しの視点―子どもの意見表明権 二 父親の役割 父親としての権威を欠く戸主 戦後の父親の子育てについての対応の仕方 父権喪失時代の到来といわれる状況 父親の果たすべき役割 三 母親の役割 核家族化と母子密着の深化 フランスと日本の母親のしつけ方の相違 新しい子育て学の創造を 四 共同保育 母親のわが子への体罰の投稿に対する反響 幼児虐待 虐待された児童の状況 厚生省による幼児虐待防止策 夫婦共働き世帯の増加 夫婦による家事・育児の分担の問題 むすび 本書執筆で参照した文献 |