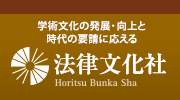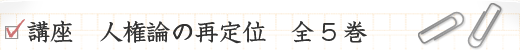- TOP
- > 講座 人権論の再定位 全5巻
- > 刊行にあたって
刊行にあたって
国家のために戦って死ぬ人々もいれば、国家によって殺される人々もいる。人権は、かかる国家権力の暴虐を抑止する理念として掲げられてきた。しかし、国家の場合と同様、人権のために戦って死ぬ人々もいれば、人権の名によって殺される人々もいる。この事実を見て見ぬふりをすることはできない。
二〇〇三年以来の米英両国によるイラク侵攻と占領はイラクによる「大量破壊兵器の開発保有」という理由の立証の失敗にも拘らず、フセイン体制による人権侵害からのイラク国民の救済の名のもとに貫徹され、救済さるべきはずの多数の非戦闘員の生命を犠牲にした。一九九九年にセルヴィア勢力によるコソヴォのアルバニア系住民虐殺に対する「人道的介入」としてなされたNATOのユーゴ空爆は、人権救済動機がより強いとみなされているが、地上軍派遣を回避した空爆はアルバニア系住民への迫害を抑止するどころか激化させ、さらにNATO軍機の安全を優先した高空からの爆撃は、民間人への「付随的被害」をほとんど故意に拡大する戦略であった。「平和国家」を標榜するわが日本においても、殺人事件被害者数が激減しているにも拘らず、「被害者の人権」が声高に叫ばれる状況の中で、死刑判決は逆に急増している。
人権の名によって人権が侵害されるという現代世界の政治状況は、人権理念に対する懐疑やシニシズムを深め、広めている。それだけではない。ポストモダン、ネオプラグマティズム、フェミニズム、闘技的民主主義、共同体論、多文化主義、アジア的価値論、「動物の権利」論、ディープ・エコロジーなど、現代思想の諸潮流は、人権理念が内包する普遍主義・権利中心主義・本質主義的人間性論・人類中心主義に対して根本的な批判を加え、人権理念の哲学的基盤を侵食しつつある。人権理念にコミットしてきたリベラリズムの陣営においても、「政治的リベラリズム」に転向した後期ロールズが典型的に示すように、リベラルな人権理念の普遍的妥当性を否認し、人権の規範的実質を希薄化し切り詰める傾向が現出している。
それにも拘わらず、現代世界では、ジェノサイド、世界中で一日に五万人(うち約三万人は五歳以下の幼児)の貧困死、民主的正統性なき政府による批判者弾圧、政治的打算による難民認定拒否など、すさまじい人権侵害が現実に横行している。すなわち、人権はいま<二重の危機>にある。一方で、人権理念は現実によって蹂躙され、他方で、その現実を批判し是正するための根拠となるべき人権理念自体の信憑性が掘り崩されつつある。
それでは、人権は現実によっても思想によっても「死せる理念」として、いずれ葬り去られるのだろうか。この悲観的な問いに「否」と明確に答えることが、本講座の目的である。そのために、本講座は<二重の企て>を遂行する。一方で、人権の意義と妥当根拠を哲学的に反省することなく、自らの政治的要求の実現戦略のみを問題にする無批判的・独善的なタイプの運動論的姿勢を排し、人権理念を根本的な批判・懐疑に応答しうるよう哲学的に再定位して、その規範的真価を的確に同定し擁護することを試みる。他方で、人権理念の哲学的正当化可能性を示すことで事足れりとし、それを蹂躙する現実をただ慨嘆するだけの講壇哲学者的態度も排して、人権実現のための、実効的にして、独善や欺瞞に陥らない批判的自己修正力をもったプロセス・方法・制度装置を探究する。
人権がいま晒されている二重の危機からこの理念を救済しうるのは、かかる二重の企てである。各巻・各論考ごとに焦点と比重の置き方に違いはあるが、人権理念の二重の危機を冷静に分析して、この理念を救済する二重の企てを分業的協業により遂行するという志向が本講座全体を貫いている。その意味において、本講座は、人権論の再定位によって人権の再生を図る共同プロジェクトである。